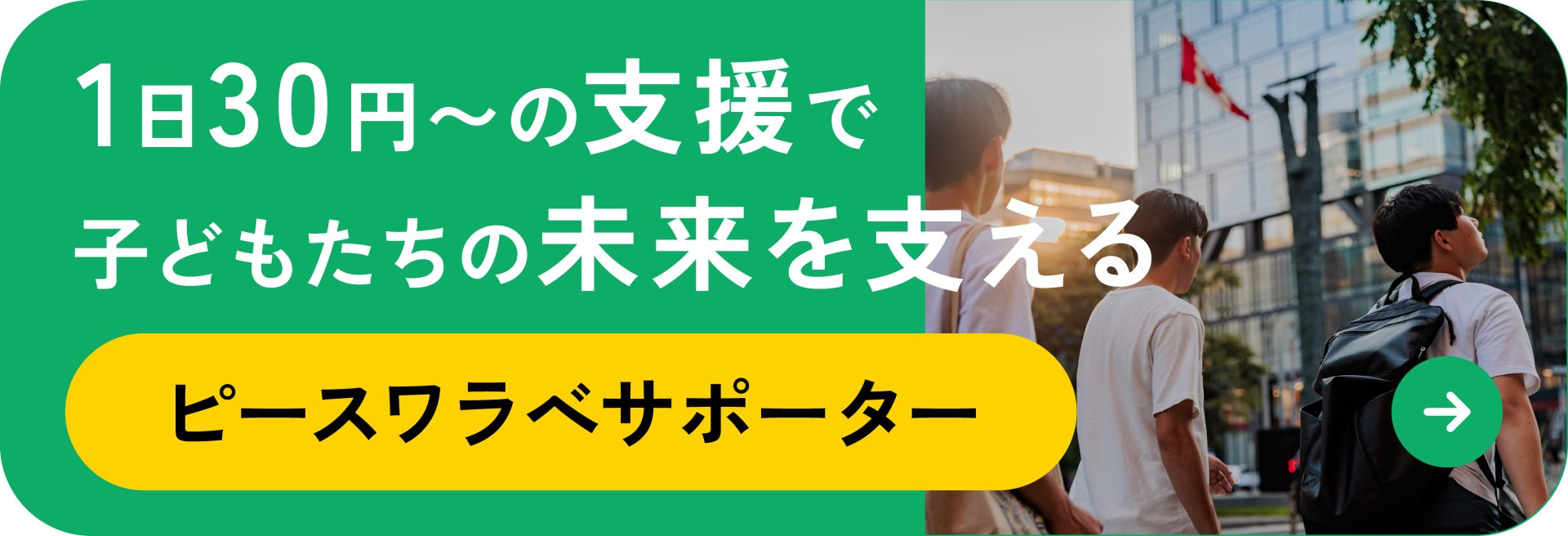子ども時代に受けた虐待が、大人になってから自分の子どもにも繰り返されてしまう……こうした「虐待の世代間連鎖」と呼ばれる問題があります。しかし、必ずしも連鎖が起きるわけではなく、支援や気づきによって食い止めることができます。この記事では、なぜ虐待が世代を超えて繰り返されてしまうのか、その原因と連鎖を断ち切るための方法を解説していきます。
虐待の世代間連鎖とは

「虐待の世代間連鎖」とはどのような事象なのか、定義や何が連鎖するのか解説していきます。
虐待の世代間連鎖の定義
虐待の世代間連鎖とは、子どもの頃に受けた虐待経験がその子どもにも連鎖してしまうことを言います。
子どもは、親の言葉や行動、態度をよく観察して学習するため、親の生き方や家庭環境は子どもに引き継がれていく傾向にあります。特に虐待やDV、貧困などは親から子へ連鎖しやすいとされているのです。
虐待をしてしまう親は、自身も子ども時代に実親からの不適切な養育を受けてきた経験がある場合が多く、30%〜50%の割合で虐待の世代間連鎖が認められたという研究結果もあります(*)。
ただし、虐待は必ず連鎖するわけではありません。子ども時代や親になったとき、適切なケアやサポートがあれば断ち切ることができます。
*)広島大学|母親の被養育経験が子ども-の養育態度に及ぼす影響
どんな連鎖が起きるのか
虐待は、言葉や暴力、愛情や生活スタイルなどさまざまな形で連鎖が起きます。たとえば子どもが自分の思うようにいかない、全然泣き止まないとしたら、過去に自分がされたように暴力や暴言で制御しようとしてしまいます。
反対に自分の話を聞いてもらえない、なかなか構ってもらえない経験が強くトラウマとして残っていれば、自分の子どもにも同じように無関心やネグレクトしてしまう可能性があります。
ほかにも言葉遣いや食事の質・頻度、遊びや勉強などさまざまな経験が、自分がされたようにそのまま連鎖していってしまうのです。
虐待の世代間連鎖の原因

虐待はさまざまな形で連鎖が起きますが、ではなぜ連鎖が起きてしまうのでしょうか。ここでは、虐待の世代間連鎖が起きる原因について解説していきます。
子育ての価値観による影響
自身が虐待を受けてきた親は、周りからきちんとしたケアやサポートを受けていない場合、愛情を持って接する子育て方法がわからず、自分の育った環境が当たり前だと思ってしまうことがあります。
子育てに正解はありません。しかし被虐待経験者は、大多数の方が想像するごく一般的な子育てを具体的にイメージすることが難しいと言われています。暴力や怒鳴り声、無視や無関心が日常的に起きていた家庭で育った子は、それが普通だと認識し、厳しいしつけや言葉などがそのまま子どもに引き継がれていくのです。
トラウマや負の感情の伝達
虐待を受けた子どもは、時に「自分は悪い子」という低い自己評価や「大人は自分を責める存在」というイメージを持ってしまいます。
そのため自分が親になり、自分の子が泣き止まなかったり言うことを聞かなかったりすると、「自分はダメな親だ」「わざと自分を困らせようとしている」と被害的認知が生じてしまうことがあります。
また、子どものときに実の親から負の感情(泣き・怒り・ぐずり等)を否定された経験があると、自分や子どもの負の感情に対して、どのように向き合えばいいのか、わかりません。結果的に、「怒る・無視する」といった自分が経験したのと同じように対応することが多く、子育てに自信がなくなってしまうのです。
愛着形成の不全
幼少期に親から十分な愛情を受けていないと、自分も子どもの愛し方や愛着形成の築き方がわからないことがあります。
子どもとどのように接し、どのように愛情が湧いていき、そしてどう愛情を表現していくのかが難しく感じられ、結果的に無関心や冷たい態度、反対に過干渉という形となって表れてしまうのです。
孤立
虐待を受けてきた人は、常に不安感や孤立感の中で過ごしていて、「人を信用できない」「頼り方を知らない」という人も多くいます。自分が子どもを育てるようになって、もし何か困りごとがあっても、誰かに「頼る」という選択肢がなかったり、そもそも誰にどのように頼ってよいのかわからないのです。
そのため一人で抱え込み、態度や言葉で子どもに当たってしまうことや、養育にエネルギーを注ぐことができず、ネグレクトぎみになってしまうことがあります。
虐待の世代間連鎖を断ち切るには

こうした虐待の世代間連鎖を断ち切るには、適切なケアやサポートが求められます。ここでは、さまざまな視点からのアプローチと、ケアをする人が留意すべきポイントについてみていきましょう。
自治体・行政の支援対策
自治体や行政では、被虐待児に対する支援や虐待の世代間連鎖を止めるための支援をしています。さまざまな対策のなかで、いくつか例を挙げてご紹介します。
【幼少期~】
児童養護施設
安心安全の生活の場の提供と、食事などの適切な生活スタイル、ケアなどを行う。
カウンセリング
虐待によるトラウマを抱えている児童や大人に対して、自分自身を肯定的に捉えられるようにし、感情のコントロールや認知行動療法などを通して心の傷の回復を図る。
【子育てへの介入(予防対策として)】
訪問型家庭教育支援
民生委員、ソーシャルワーカー、カウンセラーなどが、家庭訪問を通して相談に対応したり情報提供を行ったりする。
乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)
乳児のいる家庭を訪問して子育てに関する情報提供をしたり、乳児・保護者の心身の状況養育環境の把握を行い、養育についての相談に応じ、助言・援助を行う。
養育支援訪問事業
乳児家庭全戸訪問事業等で把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童もしくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前の支援が必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う。
地域子育て拠点支援事業
家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することで、子育ての不安感等を緩和し子どもの健やかな育ちを支援する。
ケアする人間が留意すべきこと
虐待の世代間連鎖を断ち切るためには、本人や周囲がどのようにケアをしていくかがとても重要です。ただし、ケアの場面ではいくつか注意しておきたい点があります。
まず大事なのは親を「責めない姿勢」です。
虐待を繰り返す親自身が過去の虐待によるトラウマを抱えている場合があるため、そうした背景を理解せずに対応すると、親は追い詰められてしまいがちです。
再発防止のためにも非難するのではなく、「どうすれば子どもと安心して関われるか」を一緒に考える視点が必要です。
一方で、子どもの命や安全が最優先であることは言うまでもありません。危険が及んでいる場合には、児童相談所などの専門機関による介入が不可欠となります。ケアの第一歩は「安心できる環境づくり」であることを覚えておいてください。
また、子どものうちから適切な心理的サポートを受けるかどうかで、将来が大きく変わることもあります。虐待の影響は一朝一夕で消えるものではありません。焦って短期間での解決を求めず、長期的に寄り添いながら支えていく視点が必要です。
周囲ができること
虐待の連鎖は、周囲の支えがあれば断ち切ることができます。そのために重要なことの一つは、“孤立を防ぐ”ことです。
子どものときも親になってからも、近くに自分を理解し、支えてくれる人がいることは心強いものです。親以外(施設や学校、地域)の大人から受けた愛情やサポートが、世代間連鎖を断ち切るきっかけとなるため、サポートする周囲の人は味方でいることが安心につながります。日頃から気にかけたりコミュニケーションをとったりして、小さなことでも何か変化に気づいたら、ためらわず本人や相談窓口に声をかける勇気が大切です。
まとめ
虐待の世代間連鎖は、過去の体験が未来に影響を及ぼす深刻な課題です。ただし、それは必ず繰り返されるものではありません。周囲の支援や専門的なサポート、そして「同じことを繰り返したくない」という本人の気づきによって、連鎖を断ち切ることは可能です。
子どもと親を孤立させない仕組みづくりや、地域での支え合い、相談先の周知など、私たち一人ひとりの行動が、世代を超えた虐待防止につながるのです。
【参照】
国立社会保障・人口問題研究所|児童虐待における世代間連鎖の問題と援助的介入の方略:発達臨床心理学的視点から
広島大学|母親の被養育経験が子ども-の養育態度に及ぼす影響
日本教育心理学会第61回総会|虐待の連鎖
公益社団法人 日本小児保健協会|ライフコースヘルスケアから見た虐待防止 日本教育心理学会第 回総会発表論文集|虐待の連鎖 ―男女による比較―
東京学芸大学|児童虐待の背景にある被害的認知と世代間連鎖
銀座泰明クリニック|世代間連鎖①
銀座泰明クリニック|世代間連鎖②
厚生労働省|子ども・子育て支援
大妻女子大学 人間生活文化研究所|虐待の世代間連鎖を断ち切った母親の特徴―妊娠前・妊娠中・出産後に焦点を当てて―
厚生労働省|第1章 子ども虐待の援助に関する基本事項
New post
最新記事
Category
カテゴリ
Supportご支援のお願い
どんな環境で育つ子どもも自身の未来に希望を持ち、その明るい未来を掴み取る力をつけてほしい、
私たちピースワラべはそう願って支援を続けていきます。そのためには、皆さまからの温かいご支援が欠かせません。
一人でも多くの子どもたちに、成長と学びの場を届けるために、どうかお力添えをいただければ幸いです。
Web決済以外での寄付はこちら
郵便振込
口座番号:00160-3-179641
振込先:特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン
通信欄に「国内外の子どもの教育支援事業」とご記入ください。
銀行振込
銀行名:広島銀行 油木(ゆき)支店(支店番号118)
口座番号:普通 3029477
口座名義:トクヒ)ピースウインズジヤパン
ご寄付額の最大25%を事務所の管理運営費、広報や提言活動のための費用などに活用させていただいています。ご了承ください。
銀行振り込みの場合、振り込み手数料は振込人負担となります。
銀行振込の場合、こちらでお振込人さまを特定できません。領収書がご入用でしたら、お手数ですが必ず当団体フリーダイヤルまでご連絡ください。
電話:0120-252-176(受付時間:平日10時~17時)
メール:support@peace-winds.org
クレジットカードによるご寄付は、カード会社からPWJへ入金された日がご寄付いただいた日となります。
カード会社からPWJへの入金は、ご寄付のお申し込みをいただいた日から最大で3~4ヶ月後となる場合があります。
領収証をご希望の方には、カード会社からPWJへの入金日を領収日として領収証を作成し、概ね2週間以内にお送りいたします。