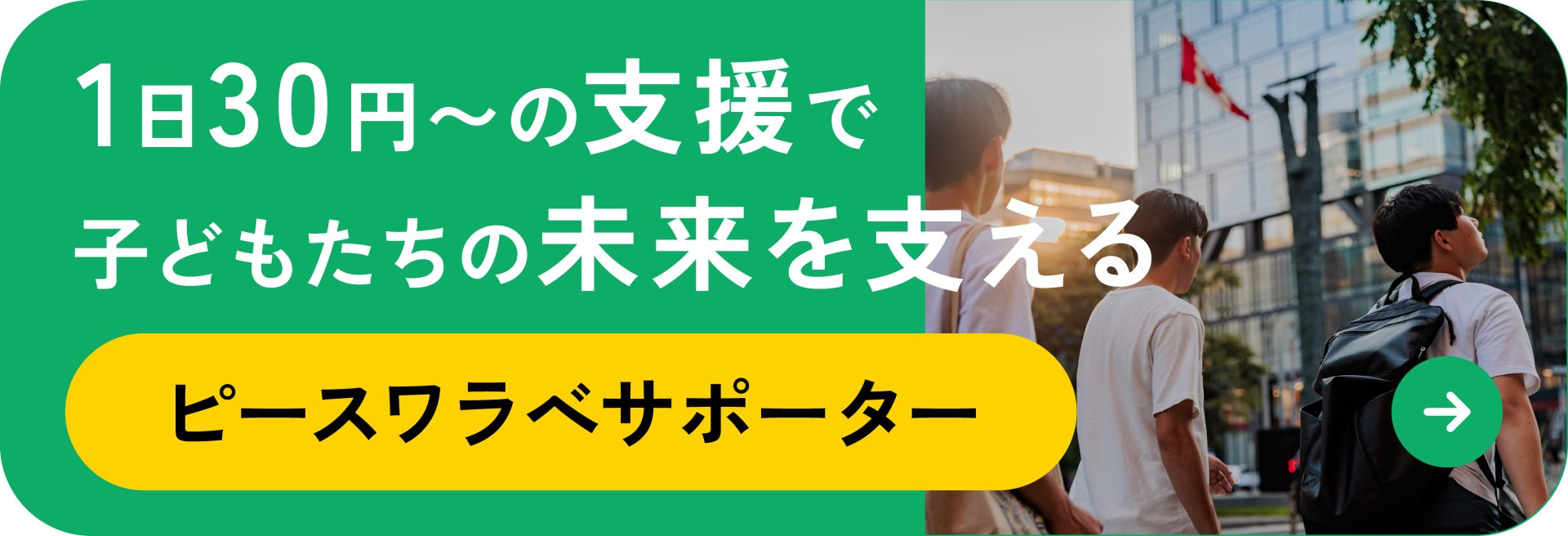子どもが希望する未来を築いていくためには、周囲が子どもを一人の人間として、また社会の一員として認め、その意見をしっかりと聞いてサポートしていくことが大切です。しかし、子どもたちが安心して自分の気持ちを話し、その声が大切に受け止められる環境はまだ十分に整えられていません。
家庭や学校で抱える不安を、言いたくても言えない子どもたちがいます。そうした子どもたちの声をすくい上げ、子どもが望む形で支えていく仕組みが「子どもアドボカシー」の取り組みです。
この記事では、子どもアドボカシーの役割や現状の課題、そしてよりよい仕組みにするためのポイントを解説します。
アドボカシーとは?子どもの権利を支える仕組み

「援護」や「代弁」「表明」などを意味する「アドボカシー」とは、さまざまな理由により自分の意思を伝えられない人たちの言葉に耳を傾け、代わりに声を挙げて行動を起こして社会課題を解決していく支援のことをいいます。
アドボカシーは、教育、医療、福祉、健康、環境、地域など多くの分野で行われます。たとえば医療や福祉の現場では、自分の意思を表明することが困難な患者さんや高齢者、障害者の方々に代わって代理人が本人の意志や権利を守る活動を行います。
困っている人の意見や権利、ニーズを把握して社会に伝え、制度の改善を訴えたり必要な支援や制度を十分に活用できたりするように働きかけるのです。
子ども福祉におけるアドボカシー
「子どもアドボカシー」は、子どもの意見を聴き、子どもの最善の利益を社会に訴えることで子どもたちの成長と活動をサポートしていきます。主に対象となる子は、以下のような子どもたちです。
・大人や社会に対して声を挙げづらい、声を拾われにくい子ども
・いじめや不登校、虐待や貧困問題により不安な気持ちや意見を言えない子ども
・児童福祉施設や病院で生活する子ども
子どもアドボカシーは、こうした子どもたちの素直な意見や声にならない声を拾い上げ、周りに伝える重要な役割を担います。
また、子ども自身が自分から意志を伝えることができるようにしていくことも、子どもアドボカシーの大切な役割のひとつです。
子どもにとって自分の意見や想いを人に伝え、それを聴いてもらい尊重されることはとても大切な経験です。そのため最近では、教育現場において子どもが自分の考えや感情を表現する力を育むことが重視されるようになりました。
「アドボカシー」と「子どもの権利条約」

「子どもアドボカシー」と「子どもの権利条約」は、密接に関係しています。
1989年に採択された子どもの権利条約を踏まえ、児童福祉法では児童の年齢及び発達の程度に応じてその意見が尊重され、子どもにとって最善の利益が優先して考慮される旨が規定されています。
それを実現するため、2022年に児童福祉法は次のように改正されました。
・子どもが意見表明する機会を確保する
・子どもの意見表明を支援する仕組みの一つとして「意見表明等支援事業」が法定化
児童福祉施設で暮らす子どもや一時保護をしている子どもの意見を、児童福祉に関する知識や経験を有する者が適切に把握し、関係機関との連絡調整を行うこととされています。
また、2024年には社会的養護を受けている子どもたちから意見を聞き、最善の利益を考慮する制度が本格的に始まりました。
すべての子どもには「意見を表明する権利」と「尊重される権利」があります。それをしっかりと守りサポートするのが、子どもアドボカシーの役割となります。
子どもアドボカシーを支える“アドボケイト”とはどんな人?

「アドボケイト」とは、法的手続きにおいて個人や団体に代わって発言し実施する人を言います。主にスクールソーシャルワーカーや社会福祉士、看護師や介護士、NPO法人の団体職員などがその役割を担うのが一般的です。
アドボケイトに特に資格はなく、必要な知識やスキルを自治体やNPO法人などの団体が研修や講習などを実施し、人材を育成しています。
アドボケイトに求められる主な目的は以下の3点です。
①本来持つ権利を守り本人の意思を最優先すること
②情報と選択肢の提示
③不利益や不平等の是正
子どもアドボケイトは、子どもの味方となって親や施設、学校や行政などからは独立した立場にあり、周りの大人たちが本人の声を受け止められるように働きかけます。
そのために、表明されづらい子どもの意見や想いを正確に代弁すること、また自己決定を尊重することが、子どもアドボカシーを実践するうえで大きなカギとなります。
現場での関わり方
子どもアドボカシーは、児童養護施設、学校、病院、福祉現場など子どもが関わるさまざまな現場で実施されています。
これらの現場においてアドボケイトは、子どもに寄り添う姿勢と信頼関係を築くことが重要です。決して焦らず本人のペースを尊重し、子ども一人ひとりの発達やタイプに応じた説明や配慮が求められます。
そのためにはまず、安心できる環境づくりが必須です。子どもたちが自由に素直な意見を言えるような場の雰囲気づくりと、「この人は絶対に自分の味方だ」と感じてもらえるような態度や言葉がけを意識していく必要があります。
また、子どもアドボカシーの活動がアドボケイトを始めとする大人本位の結果にならないためにも、特に本人の同意を丁寧に確認することが欠かせません。
子どもアドボカシーの現状と課題とは?
子どもアドボカシーは、環境に悩み声を挙げたくても話せない子どもたちにとって必要な支えとなります。しかし、アドボカシーの活動を推進していくには、いくつかの課題があります。
認知度の低さ
まず「アドボカシー」という制度や役割が社会に十分に認知されていないことが、大きな障壁となっています。
多くの大人がアドボカシーの存在や必要性を理解していないだけでなく、子ども自身も「自由に意見してよい」「相談してよい」という基本的な権利があることを知らない場合が少なくありません。そのために、子どもが困難な環境や助けを求めたい状況にあっても声を挙げる機会に恵まれず、支援につながりにくい状況が生まれてしまっています。
大人が中心の構造
子どもアドボカシーを実施するためには、子どもを主体として扱わなければなりません。しかし、大人が「こうだろう」と子どもの気持ちを勝手に判断し、子ども自身の本当の気持ちが確認されないまま物事が進んでしまうことがあります。
特に学校や医療機関などでは、子どもが本音を言いづらい構造が残っています。「子どもの意見を聞く」ことはできても話を形式的にヒアリングするだけで終わってしまい、その後の流れは大人の都合による意見や判断が優先されてしまうケースが少なくありません。
その背景には、子どもを「まだ知識や理解が足りない」あるいは「守るべき存在」と捉え、無意識のうちに子どもの意見を軽視してしまっているという現状があります。
アドボケイトの不足
アドボケイトの人材不足も重大な課題です。アドボケイトには、子どもの権利に関する深い理解、傾聴や対話のスキル、倫理的な判断力などが求められます。
しかし、そもそもアドボケイトの存在が認知されていないことに加え、人材育成の体系や研修環境が十分整っていない地域も多く、担い手の数も限られています。その結果として、子どもに寄り添った対応ができる人材が不足し、地域や人によって支援の質に差が生じることも課題のひとつとされています。
子どものアドボカシーがもっと尊重されるために

社会ではまだまだ「子どもが意見を言うこと」に抵抗を示す大人も多く、権利主体として子どもを尊重する文化が十分に根づいていません。そのため、アドボカシー活動が“特別なもの”として扱われがちです。
この問題を解決するためには、社会の意識を変えていく必要があります。たとえば、子どもたちにとって身近な教育機関や地域での情報発信が欠かせません。保護者や教師、地域住民を対象とした研修を実施したり、学校で子どもの権利について親子で学ぶ機会を設けたりすることが、「子どもには意見を尊重される権利がある」という認識を広め、理解を深めていくことにつながります。
また、アドボケイトの役割を担う人材の育成も大きな課題です。研修や資格制度を充実させ、子どもに寄り添える担い手を育成する環境づくりを整備していく一方で、子どもが安心して話せる「第三者」の相談窓口の設置や、子どもが日常的に意見を言える「参加の場」をつくることも同時に進めていく必要があるでしょう。
こうした取り組みを積み重ねることが、子どもアドボカシーが社会にとって不可欠な仕組みとして定着していき、子どもが尊重されながら成長できる環境がより確かなものとなっていくのです。
まとめ
子どもアドボカシーは子どもの権利を守り、子どもたちが安心して自分らしく過ごすために欠かせない取り組みです。しかし、子どもアドボカシーの活動を推進していくうえで、人材不足や周囲の理解不足など課題も少なくありません。
子どもアドボカシーの活動を広め社会に浸透させていくためには、子どもの声を一時的に聞くだけでなく、尊重し、さまざまな意思決定に反映する姿勢を社会全体が持つことが求められます。
大人が「代弁者」として支えると同時に、子ども自身が安心して声を出せる環境を整えていく、その積み重ねが子どもたちが安心して健やかに成長していく環境づくりへとつながっていくのです。
New post
最新記事
Category
カテゴリ
Supportご支援のお願い
どんな環境で育つ子どもも自身の未来に希望を持ち、その明るい未来を掴み取る力をつけてほしい、
私たちピースワラべはそう願って支援を続けていきます。そのためには、皆さまからの温かいご支援が欠かせません。
一人でも多くの子どもたちに、成長と学びの場を届けるために、どうかお力添えをいただければ幸いです。
Web決済以外での寄付はこちら
郵便振込
口座番号:00160-3-179641
振込先:特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン
通信欄に「国内外の子どもの教育支援事業」とご記入ください。
銀行振込
銀行名:広島銀行 油木(ゆき)支店(支店番号118)
口座番号:普通 3029477
口座名義:トクヒ)ピースウインズジヤパン
ご寄付額の最大25%を事務所の管理運営費、広報や提言活動のための費用などに活用させていただいています。ご了承ください。
銀行振り込みの場合、振り込み手数料は振込人負担となります。
銀行振込の場合、こちらでお振込人さまを特定できません。領収書がご入用でしたら、お手数ですが必ず当団体フリーダイヤルまでご連絡ください。
電話:0120-252-176(受付時間:平日10時~17時)
メール:support@peace-winds.org
クレジットカードによるご寄付は、カード会社からPWJへ入金された日がご寄付いただいた日となります。
カード会社からPWJへの入金は、ご寄付のお申し込みをいただいた日から最大で3~4ヶ月後となる場合があります。
領収証をご希望の方には、カード会社からPWJへの入金日を領収日として領収証を作成し、概ね2週間以内にお送りいたします。